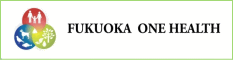令和7年1月17日
自分らしく主体的に生きていく力とも言える「非認知能力」を高めることを意識したときに、愛着形成の重要性は避けて通れません。
愛着形成とは人が特定の他者と感情的な絆を結ぶプロセスと言われており、乳幼児期における養育者等との間で形成されます。イギリスの心理学者ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)の提唱する愛着理論では、幼少期に安定した愛着が形成されると、自己肯定感に良い影響を与えたり、健やかな人間関係の形成に繋がったりします。そして、それが良好なセルフマネジメントに繋がると説明しています。
前回のコラムの中で、非認知能力の視点として「自己統制(セルフマネジメント)」や「他者と協働することができること(コミュニケーション)」は中心的な能力であると記しました。それらを基盤として他者の想いに耳を傾けたり、自分の思いや考えを探求したり、発信(カンバセーション)したりしながら、今目の前にないものを創造し状況の変化にも臨機応変に対応する力を身に付けていくと考えられています。これらのことから、やはりこの愛着を形成することは、非認知能力を高める上でとても大切なプロセスであると考えます。
では、その愛着形成を支えるには、子ども達とどう向き合っていけばいいのでしょうか。そのポイントとして、幼少期の子どもの要求(泣く、声をあげるなどで発信)に対応し安心感を与えることが挙げられます。例えば、抱っこやスキンシップなどの身体的な接触、ポジティブな対話や子どもの言葉の受容、子どもの気持ちへの共感的な反応などが有益だと言われています。
「幼少期ということは、愛着形成は児童期では手遅れなの???」
と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。
上記に挙げたような関わりや、今出来ていること、がんばれていることを「よくできたね」や「○○さんが、がんばっていることが嬉しい」などと言葉にして伝えながら対話する時間を大切にしてみてください。また、学童期は仲間(友達)との安定した安心な関係性の中でも愛着は形成されると言われています。